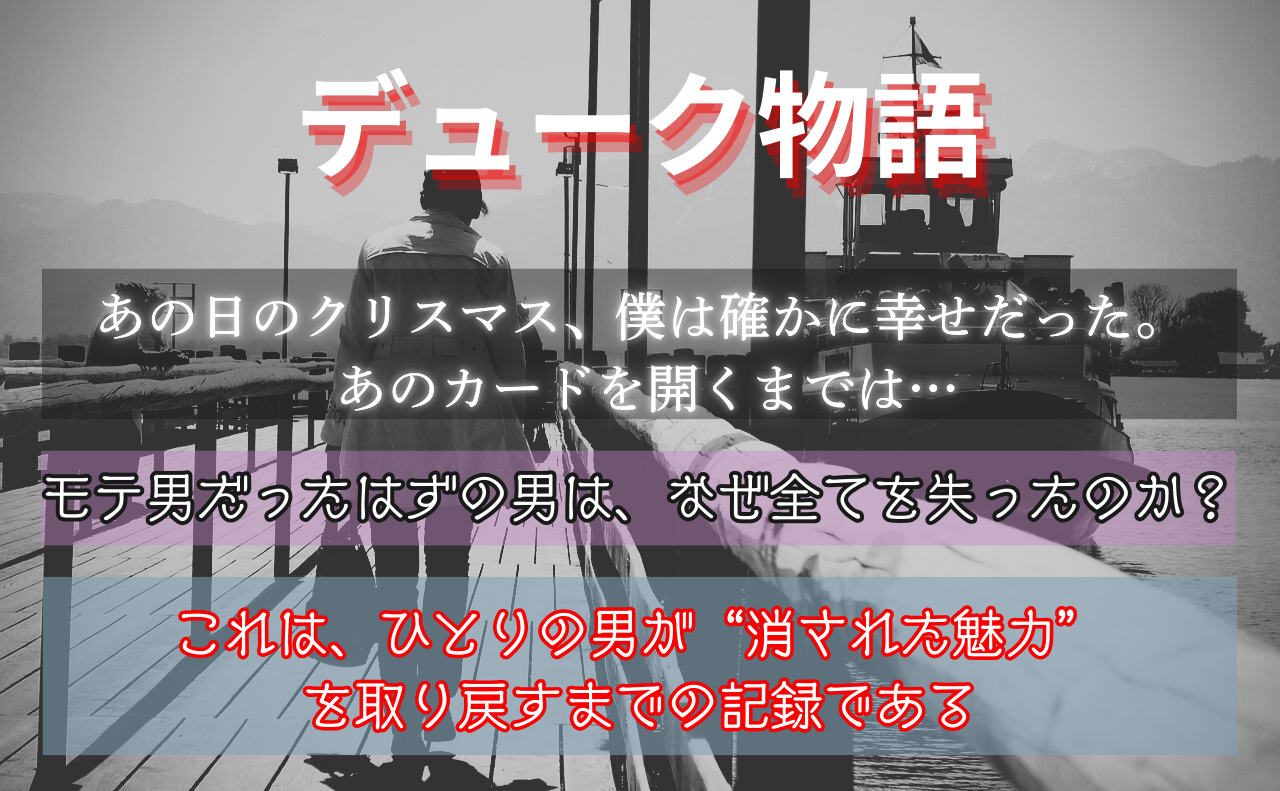昔から、どこか影のほうが落ち着いた。
人前に立って騒ぐタイプじゃないのに、
なぜか視線だけは集まってくる。
そんな立ち位置が、気づけば僕の定位置になっていた。
50代の今でも「40代に見える」と言われるのは、
若いからじゃなくて、
削ぎ落とされて残ったものが
いつの間にか雰囲気になっていたんだと思う。
12年の結婚生活が終わった理由は、正直あまり綺麗じゃない。
まあ…端的に言えば、
僕は、ちょっとだけ好かれすぎた。
夜道を歩けば、
誰かの視線が少しだけ温度を帯びて届く時期があった。
話す相手が変わるだけで空気が動く。
近づく距離で、嫉妬が生まれる。
気づいたら、ファンクラブができていた。
僕はいつも
人の感情がざわつく中心にいた。
銀行員、会社員、エステティシャン、ホステス。
昼の世界も、夜の世界も、
境遇の違う女性たちがなぜか僕の周りに集まってきた。
もちろん、彼女たちは僕に本命の女性がいると承知の上だ。
10人の女性と真剣に向き合って思ったのは、
モテってテクニックじゃなくて、
その人の中身が全部出るってことだ。
影があると人は距離を詰めてくる。
光が強すぎても、人は離れる。
そのちょうど境目を歩くのが、僕の生き方になった。
これは、
そんな影をまとった男の、
少し危なくて、ちょっと切なくて、
でも確かに前へ進んでいく物語だ。
デューク物語──
僕の再生の記録。
こんにちは、デュークです。
この物語は、
今こうして話している私とはまるで別人だった頃
勘違いと虚勢だけで生きていた過去のデューク
を赤裸々に描いたものです。
正直、思い出すだけでも胸が締め付けられる。
できることなら封印しておきたい。
そんな黒歴史です。
でも私は決めました。
あえてその過去を、今日ここで初公開します。
なぜか?
それは、
あなたに「まだ終わっていない」と気づいてほしいからです。
もし今あなたが
「自信がない」
「恋愛が怖い」
「もうオジサンだから無理だ」
そんな気持ちを少しでも抱えているのなら、
この物語は、きっとあなたの背中をそっと押すはずです。
Contents
- 1 【鼻高々の天狗だった嫌な奴】
- 2 【天狗の鼻っ柱を折られた日】
- 3 【最愛の女性との別れ】
- 4 【モテオジへ変身】
■ 自信ゼロだった私が、「俺はもう大丈夫だ」と言えるようになるまで
かつての私は、
周りからどう見られているかばかり気にして、
強そうに振る舞い、
モテているフリをし、
弱さを見せることが怖くて仕方なかった。
自分の価値は他人が決めるものだと本気で思い込んでいた。
そんな男が、
どうやって崩れ、
どうやって立ち上がり、
どうやってモテオジとして再生していったのか。
この物語は、私が一度すべてを失い、そこからもう一度“男として立ち上がる”までの軌跡だ。
■ ほんの一歩で人生は変わる
その一歩は、意外なほど小さい。
この先に書かれているのは、
気持ちよく綺麗に成功していく話ではない。
むしろ逆だ。
恥ずかしくて、
情けなくて、
胸を刺すような失敗ばかりだ。
でも、
そのすべてが“再生計画”へつながる伏線だった。
当時は気づいていなかった。
でも今は確信している。
あの頃の崩壊があったから、
今の私はここにいる。
■ では、物語を始めよう
54歳の男が、
どうやって本当の魅力を手に入れ、
人生の後半戦を輝かせていったのか。
あなたの人生を変える “ヒント” は、
たぶんこの物語の中のどこかにある。
さあ、ページをめくってください。
【鼻高々の天狗だった嫌な奴】

正直に言うと、当時の私は
「自分は特別な存在だ」
と、本気で信じ切っていた。
冷静に思い返せば、何一つ根拠なんてない。
大した実績もない。
圧倒的に魅力があったわけでもない。
ただ
・若さ
・勢い
・ちょっと整った見た目
・周りからチヤホヤされる環境
この些細な要素だけで、私は勘違いを育て続けていた。
まるで自分が
物語の主人公
であるかのように錯覚していたのだ。
鏡に映る自分を見て、
「まあ、悪くないな」などと自分に酔い、
女性から向けられる一時的な好意を
実力と勘違いした。
本当は自信なんかじゃなかった。
ただの麻酔だった。
自分の弱さに気づかないふりをするための麻酔。
現実を直視したら痛みに耐えられないから、
自分を誤魔化し続けるしかなかった。
にもかかわらず、私は堂々と胸を張り、
あたかも選ばれる側の男であるかのように振る舞っていた。
実際、自分から女性に告白したことは一度もない。
ただ単にこう思っていたからだ。
「俺から行かなくても、どうせ向こうが来る」
今思えば寒気がするほど痛い。
自分で書いていても笑ってしまうほど浅い男だった。
それでも当時の私は本気だった。
本気で「寄ってくる女性=自分が優れている証拠」だと思い込んでいた。
そして、そんな勘違いの天狗野郎だった私は、
女性を大切にするどころか、
「選ぶ側」だと信じて疑わなかった。
「俺は特別だ」
この呪文が、当時の私の自尊心を辛うじて支える唯一の柱だった。
そしてその柱の脆さに気づくのは、
まだずっと先の話だ。
●選ばれた側の男だと思い込んでいた頃
にもかかわらず、当時の私は、
自分をまるで 選ばれる側の男 だと勘違いしていた。
街を歩けば、
自分に視線が向いている気がする。
飲みの席では、
ちょっと笑いかけられただけで
「俺に気があるのか?」と妙な自信を持つ。
女性が優しくしてくれれば、
それだけで
「ああ、また俺の魅力に気づいたのか」
と勝手に物語を作り上げていた。
本当はただの社交辞令なのに。
ただの愛想笑いなのに。
ただの会話の流れなのに。
それらをすべて好意だと受け取ってしまう、
今思えば 痛々しいほどの自己中心的フィルター を通していた。
そして、その勘違いはだんだんと
日常へ侵食していく。
誰かが連絡をくれれば、
「ああ、やっぱり俺は求められてる」と思い込み、
連絡が来なければ、
「忙しいんだろう」と都合よく解釈し、
距離を取られれば、
「俺に気を遣ってるだけだな」と勘違いする。
現実と自分の認識が、どんどんズレていく。
だが当時の私は、そのズレに気づく余裕すらなかった。
なぜなら、その勘違いを手放した瞬間、
自分の心が崩れてしまうことを
どこかで本能的に分かっていたからだ。
だからこそ、
私は自分を選ばれる男という設定にしがみつき、
その設定を守るために、
強気で、無敵で、余裕のあるふりをし続けた。
だがその演技は、
後に自分の首をしめる鎖となる。
まだ誰も知らない。
そして本人すら気づいていない。
この勘違いこそが、
後の崩壊を引き起こす原因だったということに。
●女性を“点数”で判断していた最低な男

今だから正直に言えるが、
当時の私は本当に最低だった。
女性を見るたび、心の中で無意識に採点していた。
綺麗なら加点、
そうでもなければ減点。
まるで自分が審査員にでもなったつもりで、
女性を評価していた。
本当に情けない。
だが、あの頃の私はそれを当然だと思っていた。
そしてもっとタチが悪いのは
自分の点数に対して、誰よりも甘かったことだ。
鏡を見れば「まあ悪くない」と思い、
女性が微笑めば「俺に気がある」と思い、
誘われれば「選ばれた」と思い込んでいた。
全部、勝手な妄想だ。
それなのに、
私はその妄想を事実として扱っていた。
そして、その勘違いが生む歪みは、
女性への態度に露骨に現れた。
綺麗な女性には丁寧に。
そうでない女性には雑に。
気になる女性には優しく。
そうでない女性には適当に。
まるで、
自分が女性の人生の選択権を握っているかのような態度
をとっていた。
そんなある日、
私の不用意な一言で泣いてしまった女性がいた。
普通なら胸が痛む場面だろう。
だが当時の私は、
その涙に向き合おうとさえしなかった。
「仕方ない。そういうつもりじゃなかったんだし」
「ちょっと勘違いさせただけだろ」
「まあ…こういうこともあるよな」
こんな風に自分に言い聞かせ、
その場をなかったことにした。
だが本当は、
その涙は 私の心の薄っぺらさを映す鏡 だった。
自分の弱さ、
幼さ、
未熟さを直視したくないから、
見て見ぬふりをしていただけ。
さらに悪いことに、
女性に優しく接するときでさえ、
その裏にはこんな意識があった。
「好かれたいから優しくする」
「嫌われたらプライドが傷つくから優しくする」
それは優しさではなく、
ただの自己保身だった。
こんな最低な男が、
恋愛で本気の信頼を得られるわけがない。
だが当時の私は、
その当然の因果すら見えていなかった。
最低だ。
でもこれが、あの頃の“リアルな私”だ。
●なぜか分からない “無敵感”
今思えば、あの頃の私は
自信家でも余裕のある男でもなかった。
むしろ真逆で、
少し拒絶されただけで心がグラつくほど、
脆くて危うい男だった。
そんな脆さを隠すために、
私はいつも“無敵のふり”をしていた。
まるで鎧を着るように、
強い自分像を全身に貼りつけて生きていた。
だがそれは鎧ではなく、
薄いアルミホイルのような虚勢 だった。
ちょっと強めの言葉を投げられれば凹み、
気になる女性に既読スルーされれば眠れず、
予定が埋まっていない日曜が来れば不安になる。
そのくせ口だけは一丁前で、
平気でこんなセリフを吐いていた。
「俺を選ばない女なんて、見る目がない。」
恥ずかしさで胸が痛くなる。
だが、これもまた当時の真実だ。
今思えば、あれは強さではなかった。
あれは、
自分の弱さがバレるのが怖い男が吐いていた“必死の言い訳”
だったのだ。
本当の私は、
拒絶が怖くて、
嫌われるのが怖くて、
自分から行動すると傷つく気がして、
ただ来るものに乗っかるしかできなかった。
その行動力のなさを誤魔化すために、
「選ばれし男」という設定を作り、
その設定で自分を守っていた。
だが、その設定を守ることばかりに必死で、
内側の弱さは少しも解決されていなかった。
むしろ、弱さはどんどん肥大し、
虚勢は薄くなり、
強いふりは日に日に苦しくなっていく。
その苦しさを見ないようにするために、
さらに強い言葉を吐き、
さらに余裕のフリをし、
さらに女性に強気に出た。
そして気づけば、
強がれば強がるほど
少しの拒絶で致命傷を負う構造 になっていた。
●調子に乗っていた裏で、女性を泣かせ続けていた
表では威勢よく振る舞い、
「俺は選ばれる側の男だ」と強がっていた裏で、
私は知らぬうちに何人もの女性を泣かせていた。
いや、正確に言えば
泣かせている現実から逃げ続けていた だけだ。
気になる女性には甘い言葉を並べ、
都合が悪くなると距離を置き、
好意を感じれば優しくし、
飽きれば急に冷たくなる。
その行動のすべてが、
女性の感情を乱し、傷つけ、振り回していた。
にもかかわらず、当時の私は平然とこう考えていた。
「別に悪気はないし。向こうが勝手に期待しただけ。」
「俺はただ優しくしただけだ。」
「泣くほどのことじゃないだろ。」
最低だ。
今思い返しても、胸がざわつく。
だが当時は、本当にそう思い込んでいた。
なぜなら、女性の涙と向き合うことは、
自分の未熟さと向き合うこと
になるからだ。
優しくした理由は優しさではない。
嫌われるのが怖かっただけ。
曖昧な態度をとった理由は思いやりではない。
自分の気持ちがハッキリしていないのがバレるのが怖かっただけ。
そして、女性が泣いたときに逃げたのは、
彼女を傷つけたからではない。
自分の責任を認めた瞬間、
理想の自分像が崩れるのが怖かったから。
私は常に自分を守るために行動していた。
相手ではなく、いつも自分の傷つかない選択をしていたのだ。
そんな私の態度に、
最初は優しかった女性たちも、
徐々に違和感を覚え始め、
距離を置き、
そして静かに離れていった。
だが当時の私は、その理由を理解できなかった。
理解しようともしなかった。
気づけば、
気持ちの通い合う関係など一つも残らず、
ただ表面的な関係だけが増えていった。
そして、その薄っぺらい関係こそが、
後に私の人生を揺さぶる
決定的な崩壊の前兆
だったのだ。
当時の私はまだそれに気づかず、
今日もまた天狗の鼻を高くしたまま、
女性たちの心から静かに遠ざかっていくのだった。
●気づかぬまま落下していく前兆
調子に乗り続けていた私は、
その裏で何が起きているのかにも気づかないまま、
ゆっくりと落下の道を歩いていた。
いや、正確に言えば
気づいていたけれど、見ないふりをしていた
という方が正しい。
まず最初に変わったのは、女性たちの反応だった。
以前なら当たり前のように返ってきた返信が、
気づけば短く、そっけなくなる。
会ったときの笑顔が、
どこか作り物めいて見える。
「また誘ってね」と言われたはずなのに、
こちらから誘うとやんわり断られる。
それでも私は、鈍いわけではなかった。
胸の奥にわずかな違和感は確かにあった。
ただ
それを認めた瞬間、
私の天狗の鼻は粉々に折れてしまう。
だから、気づかないふりをした。
「忙しいんだろ」
「たまたまだよな」
「俺のことを気にしすぎて距離置いてんのか?」
都合の良い解釈で、自分を守り続けた。
しかし現実は残酷だ。
少しずつ、しかし確実に、
女性たちの心は離れていった。
・笑わなくなる
・会話が浅くなる
・予定が合わなくなる
・相談されなくなる
・私への興味がなくなる
そうやって距離はゆっくり、だが確実に広がっていく。
まるで、
足元の地面がひび割れていくように。
しかし私は、ひび割れた地面を見てもなお、
「これは地面じゃない。影だ。」
と自分に言い聞かせていた。
そうしないと、本当の自分の価値が透けて見えてしまうから。
その価値が想像よりも低かったら
私という存在が崩れてしまう。
だから、私は見ないようにした。
気づかないふりをして、
今日も天狗の鼻を高く上げて歩いた。
だが、目を背けた現実は、
私が気づかないうちに静かに牙を研いでいた。
そしてある日、
その牙は思いもよらぬ形で私に突き立つことになる。
【天狗の鼻っ柱を折られた日】

人生には、後になって振り返ったとき
「あ、ここから崩れ始めていたんだな」
と分かる瞬間がある。
私にとってそれは、
天狗の鼻がへし折られ、
初めて自分の弱さを直視した夜だった。
一部上場企業を退職すると決めた日。
安定や立場を象徴していた会社の名刺という“鎧”を脱いだ瞬間から、
世界の空気がほんの少し違って感じられた。
会社を辞めるという事実そのものよりも、
「鎧を失った自分」に周囲がどう反応するか が気になって仕方なかった。
しかし当時の私は、その不安に蓋をした。
「俺ならどこへ行ってもやっていけるだろ」
「俺が辞めるって知ったら、あいつら驚くんじゃないか?」
そんな、中身のないプライドを両手で必死に抱え込み、
それを自分の価値だと錯覚していた。
本当は怖かった。
名刺の肩書きがなくなった自分を見られるのが。
だが怖さに気づかないふりをして、
その夜、私はいつもの馴染みの店へ向かった。
そこだけは、
いつ来ても天狗の自分でいられる場所だと信じていたからだ。
店の前に立ったとき、
胸の奥にかすかなざわつきがあった。
だが私は、いつものように天狗の鼻を高くし、
何事もないように扉を開けた。
この時の私は、まだ知らなかった。
その小さなざわつきこそが、
これから始まる崩壊の最初の揺れ だったことに。
この夜、
私は人生で初めて選ばれない側の男になる。
●あの店に行けば、いつものようにチヤホヤされるはずだった

店のドアを開けると、
いつものように明るい店内と、
笑顔で迎えてくれる女の子たち。
「デュークさ〜ん♡」という声が飛んでくる。
席に着けば、自然と輪の中心になる。
何をしなくても、勝手に持ち上げられる。
その扱われ方が、自分の価値だと思っていた。
だからこそ、
会社を辞めると決めたあの日、
私は迷わずあの店を選んだ。
肩書きを失い、鎧が外れた不安を
いつものチヤホヤが埋めてくれる気がしたのだ。
だが本音を言えば、
あの夜、店へ向かう足取りは少しだけ重かった。
理由ははっきりしていた。
店が変わったのではない。
肩書きのなくなった自分が不安を抱えていた のだ。
いつも通りの笑顔が返ってくるだろうか?
いつも通りの扱いを受けられるだろうか?
いつも通りの「俺」でいられるだろうか?
そんな小さな不安を、
私は必死に押し込めた。
「大丈夫。俺なら今日も主役だ。」
そう自分に言い聞かせるように、天狗の鼻を高くした。
店の前に立った時、
胸の奥にかすかなざわつきが走った。
だが私は、その感覚を
「気のせいだ」と笑い飛ばし、
何事もなかったかのように扉を開けた。
もちろん、店の空気はいつも通りだ。
女の子たちの笑顔も、声のトーンも、
まったく変わらない。
変わっていたのは、
扱われる立場から、自分の立場を気にする側へと変わってしまった私 のほうだった。
その微かな揺らぎを、
私はまだ直視しようとしなかった。
この夜、
その小さな不安が現実となり、
天狗の鼻が音を立てて折れることになるとは、
この時の私は想像すらしていなかった。
席につくと、
よく話していた女の子が笑顔でやってきた。
いつもなら、その笑顔だけで
自尊心がふわりと持ち上がるのだが……
この日は、なぜか胸がざわついた。
私は何気ない風を装いながら、
ぽつりと言った。
「実はさ、会社……辞めることにしたんだ。」
その瞬間だった。
女の子は驚いた顔を見せながらも、
すぐに笑顔を作り直した。
「えっ、辞めちゃうの? もったいな〜い!でも頑張ってね!」
言葉だけを聞けば、
いつも通りの明るく優しい返事だ。
だが、
その笑顔がほんのわずかに揺らいだことを
私は見逃さなかった。
ほんの一瞬。
本当に一瞬。
けれど、私の胸に
冷たいもの がスッと走った。
その瞬間、
私は気づきたくなかった現実を
直感的に悟ってしまったからだ。
「あ……
この店で特別扱いされていたのは、
俺じゃなくて俺の肩書きだったのか?」
言葉にしたら壊れてしまいそうな疑問。
もちろん、その疑問を打ち消すように
私は大げさに笑ってみせた。
「まあ次のステージってやつだよ。」
すると彼女は、
営業スマイルを崩さずに返した。
「そっかそっか! じゃあ、また来てね〜!」
今までなら嬉しかったはずの言葉なのに、
この夜ばかりは胸の奥に微かな違和感が走った。
その違和感は、
心の奥でぼんやり灯った小さな警告灯のようだった。
だが私は、その灯りに気づかないふりをした。
気づいてしまえば、
肩書きがなくなった自分という現実を
受け入れなければならないからだ。
そのふりこそが、
後に私の心を大きく揺らすきっかけになる。
●そして、誰からも連絡が来なかった
退職を告げたあの夜、
私は帰り道で携帯を握りながら、
どこかで当然の未来を想像していた。
きっと誰かから連絡が来るだろう。
「大丈夫?」「また会おうね」と言われるだろう。
むしろ、少し心配されるかもしれない。
そんな甘い期待を抱きながら、
携帯がポケットの中で震えるのを待っていた。
だが現実は残酷だった。
一件も来ない。
既読すらつかない。
通知が一つも光らない。
時間だけが静かに流れ、
携帯は沈黙したままだった。
「あれ? 忙しいのかな」
最初はそう思った。
しかし1日経っても、2日経っても、
誰からも連絡が来ない。
その沈黙は、
まるで世界中が私から視線をそらしたかのようだった。
そして気づいた。
「あ……本当に、誰も俺のことなんて気にしてなかったんだ。」
天狗の鼻が折れる音は、
大きな衝撃ではなく、静かに響いた。
今まで特別扱いだと思っていたものは、
ただの営業トークでしかなかったのかもしれない。
私が勝手に物語を作り、
勝手に自分を主演にしていただけ。
それが現実に引き戻された瞬間、
胸の奥で何かがストンと落ちた。
連絡が来ないという事実は、
拒絶ではなく、
完全な無関心を意味する。
拒絶よりも残酷な、
透明人間になる感覚。
その感覚は、
想像以上に胸に刺さった。
私はこのとき初めて、
自分がどれほど脆い自尊心にすがって生きていたかを思い知らされた。
連絡が来ない携帯を見つめながら、
気づけば私は、
自分でも想像していなかった言葉を呟いていた。
「……俺って、こんなに価値なかったのか?」
天狗の鼻が折れる瞬間とは、
誰かに叱られることでも、
失敗することでもない。
誰にも必要とされていなかったと知ること。
その事実こそが、私の心を深く貫いた。
●あれだけ拒否していた連絡を、今は自分が待っているという現実
連絡が来ない日々が続き、
私はついに、ある現実を認めざるを得なくなっていた。
「……誰も、俺に興味がなかったんだ。」
そのことに気づいた瞬間、
胸の奥がズキリと痛んだ。
天狗の鼻どころか、
自尊心そのものがひしゃげていく感覚。
だが、その痛みから逃げるように、
私は“最後の望み”を探し始めた。
その望みとは
以前、押しに負けて連絡先を交換した“中の下のキャバ嬢”。
普段なら絶対に連絡しない。
いや、連絡できない。
なぜなら、当時の私はこう思っていたからだ。
「俺は選ぶ側の男だ。
俺から追いかけるなんてダサいことはしない。」
そのプライドが、
この時ばかりは邪魔でしかなかった。
誰からも連絡が来ないという地獄に、
私はゆっくりと沈んでいった。
そしてついに、
天狗の自分ではなく、
弱い自分の指が携帯を開いた。
震える指先で、
彼女の名前をタップした。
画面が開く。
そこには
一度もこちらから送ったことのない、空白のメッセージ欄
が広がっていた。
その空白が、
まるで自分の心の空洞を映しているようだった。
情けなさを押し隠すように、
私は短く送った。
「久しぶり。元気?」
送信ボタンを押した瞬間、
胸の奥に何かが壊れる音がした。
私は、かつて自分が「下」と見ていた相手に、
救いを求めるように連絡しているのだ。
プライドがひしゃげ、
自尊心が潰れ、
男の格好がつかない。
そのすべてを自分が一番理解していた。
だからこそ、
返信を待つ間の沈黙は地獄だった。
5分、10分、30分……
その間、私はずっと携帯を握りしめ、
天狗の自分が壊れていく音を聞いていた。
やがて悟る。
「俺が避け続けた現実は、
こうやって牙をむくんだな……」
返信は結局、その日も、翌日も来なかった。
私は涙が出るほど情けなく、
涙が出るほど孤独だった。
そしてその孤独の中で、
私は初めて自分の本当の姿を見た気がした。
●“俺は特別”はただの幻想だった
誰からも連絡が来なかった日々を過ごすうちに、
私はようやく気づき始めていた。
いや、正確に言えば
気づいていたのに、ずっと認めたくなかっただけだ。
私がしがみついていた
「俺は特別な男だ」
という自信は、ただの幻想だった。
女性にチヤホヤされること、
店でちやほやされること、
肩書きがあることで扱いが変わること。
それらはすべて、
本当の自分の魅力とは何の関係もなかった。
私は自分の価値を
他人の態度に預け続けていただけ。
女の子が笑えば、自分も価値があると錯覚し、
連絡が来なければ価値が揺らぐ。
そんな不安定な土台の上に、
私は特別という城を建てていたのだ。
そしてその城は、
誰からも連絡が来なかったあの沈黙の夜に
音もなく崩れ始めた。
その時、初めて認めざるを得なかった。
「俺が特別だったんじゃない。
俺が特別だと思い込んでただけなんだ」
その気づきは、
胸にナイフを刺されたように痛かった。
なぜなら、
特別な自分という幻想を捨てた瞬間、
私はただの孤独な男に戻ってしまうからだ。
だが同時に、
その痛みの奥に、別の感情が生まれ始めていた。
それは、
本当の自分で生きられるかもしれない
という、ごく小さな希望だった。
幻想が壊れ、
虚勢が剥がれ、
天狗の鼻が折れ、
私は裸の自分と向き合わざるを得なくなった。
その裸の自分こそ、
後に理想人格モデルへと作り変えられる
原石の状態だったのだ。
だがこの時の私は、
そんな未来が待っていることなど知る由もない。
ただ、
静かに崩れていく自分を感じながら、
携帯の黒い画面をぼんやりと見つめていた。
●違和感は、崩壊の前触れだった
思い返せば、
あの夜に感じたわずかな“違和感”こそ、
すべての崩壊の前触れだった。
店の空気が変わったわけではない。
女の子たちの態度が冷たくなったわけでもない。
あの時はまだ、誰も私の退職を知らなかった。
それでも、胸の奥に走ったザワつきは、
確かに存在していた。
私が座った席、
向けられた笑顔、
交わされた言葉。
どれもいつも通りなのに、
いつも通りに感じない自分 がいた。
その感覚を私は
「疲れてるだけだろ」「気のせいだろ」
と何度も押しつぶした。
だが本当は知っていた。
特別扱いされる自分に、
もう自信が持てなくなっていたのだ。
会社という鎧を脱ぎ捨てた途端、
私は社会の中での立ち位置に不安を抱え始めていた。
その不安が、
いつもの笑顔を遠く見せ、
いつもの声を薄く聞こえさせ、
いつもの店を居場所ではない場所に変えていった。
あの違和感は、
ただの気のせいではなかった。
崩れ落ちる前の建物が
最初にミシッと小さな音を立てるように、
あれは
私の虚勢が最初にひび割れた瞬間だった。
そして、そのわずかなひび割れが、
数日後には取り返しのつかない“崩壊”となって押し寄せる。
この時の私はまだ、
その前兆の意味を理解していなかった。
ただ、
胸の奥で小さく鳴り続ける違和感に
耳を塞ぎ続けていただけだった。
【最愛の女性との別れ】

夜の店の女性たちから連絡が途絶えたことは、
まだ理解できた。
彼女たちにとって私は、
お金を使う客であり、
少し扱いのいい商品のような存在だったのだろう。
私という商品価値が下がれば、
離れていくのは当然だ。
そこまでは、まだ冷静でいられた。
だが
次に起きた出来事は、そんな薄っぺらい話ではなかった。
それは、私の人生の中心にいた女性。
唯一、心の底から信じていた相手。
どんな時でも味方でいてくれると信じて疑わなかった、
たった一人の存在。
その彼女との別れだった。
夜の店の女性たちの沈黙とは違う。
営業トークの消滅とは違う。
これは、
“本当の意味での喪失”だった。
この瞬間から、
私は本当に崩れていくことになる。
●本当に大切だったのは“この人だけ”だった
当時、私はひとりの恋人がいた。
彼女は、どこか特別だった。
派手でもなければ、甘え上手なタイプでもない。
少し不器用なくらいなのに、
なぜかそばにいると落ち着く人だった。
私を持ち上げることもない。
必要以上に褒めることもない。
だけど
どんな時でも、私を信じてくれた。
その「信じる」という姿勢が、
私には何よりの救いだった。
彼女の前では、
虚勢を張る必要もなかった。
強がらなくてもよかった。
天狗の仮面をかぶらなくてもよかった。
唯一、
素のままの自分でいられた相手だった。
思えば、他の女性からどんなにチヤホヤされても、
本当に心が休まる瞬間は彼女といる時だけだった。
正直に言えば
他の女性たちがどれだけ笑顔を向けてくれても、
私の人生に本当の意味で影響を与えていたのは、
彼女ただひとりだった。
そんな大切なことに気づくのは、
いつも失ってからだ。
●あの日のクリスマスは、誰が見ても幸せそうに見えただろう

あの日のクリスマスは、
誰が見ても幸せなカップルにしか見えなかっただろう。
イルミネーションの下で笑い合い、
温かい食事を楽しみ、
他愛もない話で盛り上がり、
心も体も気づけば自然に手を繋いでいた。
彼女の笑顔には、
本当に一つの曇りもなかった。
むしろその日は、
いつも以上に優しく、柔らかく、
どこか包み込むような雰囲気さえあった。
私は完全に安心していた。
いや、油断していたと言ったほうが正しい。
彼女が隣にいることに疑いの余地もなく、
「この幸せは続くものだ」
と信じ込み、
疑うことすらしなかった。
その油断、
その驕り(おごり)、
その慢心こそが
このあと私を
底なしの地獄へ突き落とすことになる。
あの夜の笑顔が優しかったのは、
本当は最後の笑顔だったのに、
私はその意味に最初から気づけなかった。
●別れ際。紙袋一つで人生が変わる瞬間がある
デートを終え、彼女を家の前まで送ると、
彼女は、ふっと微笑みながら小さな紙袋を取り出した。
彼女
「はい、クリスマスプレゼント!」
その声は弾んでいて、
まるで子どもが宝物を渡すときのように無邪気だった。
俺
「お〜ありがとう!」
彼女
「今日も楽しかった。またね!」
彼女は、いつもと変わらない笑顔で手を振った。
その笑顔には、一滴の陰りもなかった。
温かくて、優しくて、
明日も普通に会えると疑わないような表情だった。
いつもと何も変わらないやりとり。
しかし今思えば、
あの笑顔は優しすぎた。
あまりにも綺麗すぎた。
その紙袋には、
プレゼントと一緒に
別れが丁寧に、綺麗に、包まれて入っていた。
ただの紙袋ひとつ。
されどその中身ひとつで、
このあと私の人生は
音もなく大きく軌道を変えることになる。
●家に帰り、地獄の扉が静かに開いた
家に着き、
まだ彼女の笑顔の余韻が残る中で、
私はテーブルに紙袋をそっと置いた。
「さて、何が入ってるんだろうな…」
そんな呑気な独り言を言いながら袋を開けると、
高級ブランドのロゴが入った箱が現れた。
胸が少しだけ弾む。
「まさか…あれじゃないか?」
期待に満ちたまま箱を開いた。
中には、
以前から欲しかった財布が入っていた。
「ああ、やっぱり…!」
そう呟きながら笑った。
その横に、
小さなメッセージカードが添えられていることに気づくまでは。
白いカード。
丁寧な文字。
優しい彼女らしい、
そんな印象を受けた。
私は軽い気持ちでカードを開いた。
「今までありがとう。
ずっと一緒にいられなくてごめんね。
あなたの幸せを祈っています。
さようなら。」
たったこれだけの言葉だった。
短い。
優しい。
残酷なくらい丁寧な文章だった。
胸の奥がズキンと痛んだ。
その痛みは、呼吸を奪うほど鋭かった。
カードを持つ指が震え、
急に冷たく変わった。
誰よりも近くにいたはずの彼女が、
たった数行の文字だけを残して
私の人生から姿を消したのだ。
幸せなクリスマスの光景が、
音もなく反転していく。
あの時、彼女が見せた優しい笑顔は
別れを伝えるための、最後の微笑みだった。
私は呟いた。
「……嘘だろ。」
だが現実は、
カードの文字と共に、無慈悲にそこにあった。
その瞬間、
私の中で何かが崩れ落ちた。
カードを読み終えた瞬間、
視界がぼやけた。
気づけば、涙が落ちていた。
「どうして…気づけなかったんだ。」
夜の店の沈黙とも、
中の下のキャバ嬢に無視される痛みとも違う。
これは、
私という男の中心が砕け散る音だった。
この夜、私は確かに終わった。
……時間が止まった。
あまりの静けさに、
自分の心臓の音だけがやけに響いていた。
●時が止まった
最初に出た言葉は、
「え?」
たったそれだけ。
理解できなかった。
いや、理解したくなかった。
文字は読める。
意味も分かる。
なのに、頭が拒絶していた。
心臓がドクンドクンと跳ね続ける。
視界はゆっくりと滲み、
世界が遠ざかっていくような感覚に襲われた。
「これは夢だろ?」
「何かの冗談か、別の意味があるはずだ」
そんな逃げ道を必死に探した。
気づけば、
私は玄関の方を見ていた。
彼女の家に戻って、
「どういうこと?」と聞きたかった。
聞かなきゃいけない気がした。
何かがまだ繋がっているはずだと信じたかった。
でも
足が動かなかった。
膝が笑い、
力が抜け、
ただその場に縫い付けられたように立ち尽くすだけ。
呼吸がうまくできず、
胸がギュッと掴まれたように苦しい。
目の前の現実に、
身体も心も追いついていなかった。
その瞬間、
自分の中で何かが折れたのが分かった。
「俺は選ばれる側の男だ」
そう信じて疑わなかった自尊心は、
たった一枚の紙に書かれた“さようなら”で
あっけなく粉々にされた。
何年も積み上げてきた自信が、
音もなく崩れ落ちる。
私はただ、
その崩壊を止めることもできず、
受け入れることもできず、
ぼんやりと立ち尽くすしかなかった。
あの夜、
時が止まったのは、
“彼女に別れを告げられたから”ではない。
自分が信じていた男としての軸が折れたからだ。
●自信が砕ける音がした
その瞬間、胸の中で
バチンッ
と何かが弾けた。
まるで、これまで張りつめていた糸が音を立てて切れたようだった。
誤魔化し続けてきた現実が、
一気になだれ込んできた。
私はずっと思っていた。
自分には魅力があり、だから女性が寄ってきていたのだと。
だが、その考えはここで完全に崩れた。
肩書き、雰囲気、夜の店での扱い。
それらはすべて、私の本質ではなく、
外側に貼りつけられた借り物の価値だった。
もし本当に魅力があったなら
一番大切な人が、こんな残酷な別れ方を選ぶはずがない。
この瞬間、私はようやく理解した。
私には魅力なんてなかった。
あったとしても、それは薄くて脆い表面だけのもの。
ステータスという名の“外付けの自信”にすぎなかった。
そして、心の底に封じ込めていた事実が
ゆっくりと浮かび上がってきた。
告白したことがないなんて、
自信満々に語ってきたけれど、それも嘘だ。
本当はできなかっただけだ。
自信がなかったから、選ばれる自分を演じていただけだった。
その事実が胸に突き刺さり、
気づけば声に出していた。
「俺って……全然魅力ないんだ。
これって完全に非モテってことだよな。」
その言葉を口にした瞬間、
自分で自分を守っていた殻が、
ガラガラと音を立てて崩れ落ちていった。
自分の中心が砕ける音を
確かに聞いた気がした。
●涙の理由は、悲しさだけじゃなかった
そのメッセージカードを読んだ瞬間だった。
胸の真ん中に“穴”が空いたような感覚がした。
悲しいとか、ショックとか、
そんな単純な言葉では片づけられない。
これは
ずっと隠してきた本当の弱さを、強制的に突きつけられる痛みだった。
私は自分を、どこかで
「選ばれる側の男」
だと思い込んでいた。
強く見せれば本当に強くなれる気がしていたし、
余裕のある男を演じれば、それが自信になると思っていた。
でもそれは全部、つくられた自信だった。
彼女の一枚のカードが、それを容赦なく引き裂いた。
心の底に押し込めていた不安も、孤独も、
本当の自分への失望も、一気に溢れ出してくる。
逃げ続けていた弱さを、
初めて直視させられた。
その瞬間の痛みは、
誰かに拒絶された痛みではなく、
自分自身に裏切られたような痛み
だった。
胸の奥がズキズキと締めつけられ、
息を吸うのも苦しい。
膝から崩れ落ちた時、
ようやく理解した。
ずっと自分をごまかして生きてきたんだ、と。
そう気づいた瞬間、
胸の痛みが少しだけ柔らかくなった気がした。
ずっと無理をしていた部分が限界を迎えた
そんな感覚だった。
ゆっくりと涙がこぼれた。
止めることもごまかすこともできなかった。
これは、拒絶されたから流れた涙ではない。
本当の自分を初めて正直に見たときに流れる涙
だった。
この崩壊がなければ、
私は永遠に天狗のままだっただろう。
そして
本当の自分がようやく顔を出した夜
だったのかもしれない。
【モテオジへ変身】

気づけば、私は
職なし、モテない、ただのオジサン
そんな三拍子が揃った男になっていた。
少し前の私なら、
そんな未来が自分に訪れるなんて想像すらしなかった。
失恋、信頼の崩壊、自尊心の喪失。
長年まとってきた肩書きやプライド、
そしてモテの幻想まで、
全部まとめて剥ぎ取られた。
朝目が覚めても、
胸の奥に空洞があるだけで、
生きている実感がほとんどない。
ふと鏡を見る。
そこに映っていたのは、
以前の私なら見向きもしなかったであろう、
覇気のない中年男だった。
駅前に立っていたら、
誰の記憶にも残らないような男。
そんな自分が、鏡の向こうにいた。
その姿を見た瞬間、
胸の奥がじんわり痛んだ。
今まで私は、
自分がいちばん信じていた
「デューク像」
を必死に守っていた。
選ばれる男。
余裕のある男。
モテる男。
強い男。
でも、その像は幻だった。
誰よりも私自身が、それを信じたかっただけだ。
目の前の鏡に映るのは、
その幻が崩れた後に残った、
ありのままの私だった。
弱い。
自信がない。
何者でもない。
だけど、不思議なことに、
その姿をじっと見つめていると、
ほんの少しだけ、胸の奥が軽くなる瞬間があった。
「これが本当のスタートなのかもしれない」
そんな言葉が、ふっと脳裏をよぎった。
崩れきったところからしか、
新しい何かは始まらない。
このどん底の時間が、
後に私を「モテオジへ変える歯車」を
ゆっくりと回し始めることになる。
まだこの時の私は、
その変化の始まりに気づいていなかった。
●「女性なんてもう信じない」そう言いながら、本当は…
最愛の女性に去られたあと、
私はただ傷ついただけでは済まなかった。
心にできた穴は想像以上に深く、
そこからゆっくりと何かが漏れ出していくような、
そんな感覚が続いた。
気づけば私は、
女性だけでなく、人そのものを
どこか警戒するようになっていた。
信じたら裏切られる。
期待すれば失望する。
寄りかかれば、折れたときに立っていられなくなる。
そんな経験をしたからこそ、
私はいつの間にか、
「誰も信じないほうが楽だ」
という考え方に落ち着いてしまった。
そして、強がるように言っていた。
「女性なんて、もう信じない。」
周りから見れば、私は
失恋を乗り越えた強い男に見えたかもしれない。
ひとりで生きていけそうな、
誰にも頼らないタイプの男に見えたかもしれない。
だが、それは表向きの私だ。
実際には、
誰も必要としない男を演じていただけだった。
その演技は、
自分を守るための鎧のようなものだった。
でも、心の奥底では違う声がずっと鳴っていた。
もう一度愛されたい。
もう一度「あなたじゃないとダメ」と言われたい。
その願いを認めるのが怖かった。
弱い自分が嫌だった。
再び傷つくのがたまらなく怖かった。
だから私は、平気なふりをし続けた。
飲み会に行っても深い話はせず、
仕事で何を褒められても心が動かず、
休日はただ時間を潰すように過ぎるだけ。
孤独というよりも、
「人と繋がる感覚がなくなった男」
になっていた。
それでも心のどこかで、
かすかな温もりを求めている自分がいた。
しかし、その本音を認めることは、
その頃の私にはできなかった。
弱い自分を許す勇気がなかったからだ。
けれど今振り返れば、この矛盾だらけの日々こそが、
再生への一歩だったのだと思う。
強がりと本音の間で揺れていたあの時間があったからこそ
のちに私は、自分の本当の在り方を探し始めることになる。
あの頃の弱さは、
実は再生計画の入口に立っていた証だった。
●あの頃の俺は、空洞を隠すために大きく見せていた
落ちぶれた私が最初にしたことは、
自分を立て直すことではなかった。
外側だけを取り繕うことだった。
「大丈夫だよ、俺は強い」
「まだやれる。余裕だよ」
そんな言葉を何度も自分に言い聞かせ、
崩れそうな心を必死に支えていた。
自信がある男に見られたかったし、
何でも一人で乗り越えられるように思われたかった。
でも
その強がりが嘘だと、私はとうに気づいていた。
夜になると、
部屋の静けさがゆっくりと忍び寄ってくる。
その静けさだけは、
どれだけ強がってもごまかせない。
「職なし。モテなし。自信なし。」
夜の部屋で、その言葉がふっと浮かんだ瞬間、
胸の奥がじんわり痛んだ。
かつての私は
「選ばれる側の男」だった。
だけど今の私は
誰からも選ばれず、誰の記憶にも残らない男になっていた。
窓の外では街の灯りが普通に瞬いている。
人は歩き、店は開き、電車は走る。
外の世界はいつも通り動いているのに、
まるで自分だけ時間が止まってしまったようだった。
置いていかれる感覚。
世界のリズムから外れてしまった感覚。
あのときの静寂は、今でもふと蘇る。
ただ静かで、
ただ苦しくて、
ただ無力だった。
誰かに頼ることもできず、
自分を信じることもできず…
今思えばあの夜の静けさは、
虚勢を脱ぎ捨てるための準備
だったのかもしれない。
あの孤独がなければ、
私は自分の内側を見つめ直すこともなかっただろう。
●そんな時だった。“あの声”が聞こえた。
ある日の昼下がり。
ぼーっとしながらコーヒーを飲んでいると、
ふいに胸の奥から声がした。
「デュークよ、もう一花咲かせようぜ」
気のせいかと思った。
でも、その言葉が妙に心に刺さった。
もう一花咲かせるなんて、
ここ数年、一度も考えたことがなかったからだ。
むしろ、何かを諦める理由ばかり探していた。
だからこそ、その言葉が鋭く刺さったのだと思う。
私はハッとした。
「オジサンでも一線で活躍している人がいる。なぜ、自分だけがくすぶっているんだ?」
その問いが胸の中で反響した瞬間、
止まっていた心の歯車が、
ゆっくりと、動き始めた。
小さな音だった。
人には聞こえないほどの微かな変化。
でも、そのわずかな動きが、
後に私を再生へ導く大きな始まりとなった。
●そこから始まった、“自分の正体探し”
あの日を境に、私は動き始めた。
まず手に取ったのは、恋愛本だった。
そこから心理学、脳科学、行動学、精神世界。
気づけば、興味のあるものを片っ端から買い漁っていた。
モテたい。
強くなりたい。
魅力を取り戻したい。
最初はそんな思いが背中を押していた。
けれど、本を読み進めていくうちに
胸の奥で別の疑問がひょっこり顔を出した。
「あれ? 俺って……自分のこと、何も知らないまま生きてきたんじゃないか?」
その気づきは、思った以上に衝撃だった。
私はずっと
女性にモテる方法や、
強く見せるテクニックばかりを探していた。
でも本の内容を深く理解しようとするほど、
私の意識は外側のノウハウではなく、
内側の自分そのものに向かっていった。
女性へのアプローチより先に、
自分の癖、心のクセ、思い込み、過去の傷……
そういったものが、次々に浮かび上がってきた。
その時、ふと気づいたのだ。
私は女性にモテる方法を探しているのではなく、
自分が何者なのかを知ろうとしていたのだ。
ずっと外の世界ばかり気にしていた私が、
初めて内側の自分と向き合った瞬間だった。
そして、今振り返れば、
この気づきこそが全ての始まりだった。
外側を変えるのではなく、
内側を整える旅がここから始まった。
●そして出会った、“本物の男”
学びを続けていたある日、
ひとりの男性の存在を知った。
その人は派手に振る舞うわけでもなく、
大きな声で自己主張するタイプでもなかった。
かといって、威圧感で人を動かすような男でもない。
ただ
落ち着き、余裕、言葉の間、眼差し、所作。
そのすべてが、自然体のまま完成されていた。
無理に魅せようとせず、
飾り立てることもせず、
それでも周囲の空気を一瞬で変えてしまうような男だった。
私は思わず心の中でつぶやいた。
「うわ…これが、ほんとにモテる男なんだ。」
羨ましさでもない。
嫉妬でもない。
もっと深い感情だった。
こういう男になりたい。
ただそれだけを、
まっすぐに感じた。
その瞬間、心の奥で何かがカチッと噛み合った気がした。
私は迷わなかった。
いや、迷えるはずがなかった。
すぐに行動した。
その男性から直接学び始めた。
外側のテクニックではない、
内側から滲み出る魅力の作り方。
強がるのではなく、
構えるのでもなく、
自然体でありながら、人を惹きつける男になる方法。
これが、のちに私がたどり着く
理想人格モデルの原型となる出会いだった。
●学びは“テクニック”じゃなかった
彼と初めて会った日。
特別な言葉を浴びたわけでも、
派手なアドバイスを受けたわけでもない。
けれど、向かい合った瞬間、
胸の奥で何かがふっと動いた。
落ち着いた空気。
丁寧で無駄のない所作。
人を圧さず、引き寄せるような自然な佇まい。
そのどれもが、本質を語っていた。
あ、モテる男って…こういう人なんだ。
その感覚がスッと胸に入ってきた。
説明ではなく、体感だった。
この瞬間、
今まで自分が信じていた
「モテの形」 が一気に書き換えられた。
テクニック?
駆け引き?
会話術?
そんなものは、
内側が整っていない男が“外側を取り繕うための道具”でしかなかったのだと気づいた。
彼の教えは、
恋愛のノウハウではなかった。
もっと深く、
もっと人間としての「核」に触れるもの
人としての在り方の土台を扱う男だった。
静かな佇まい。
整った呼吸。
落ち着いた眼差し。
自然と生まれる間。
丁寧な所作。
派手さも誇示もないのに、
その存在だけで心が整っていくようだった。
その時、胸の奥にスッと落ちた。
モテとは、技術ではなく“人格”から生まれるものなんだ。
この瞬間、
私が長年信じていたモテの概念はすべて書き換わった。
彼の教えは、恋愛講義などではない。
まるで
内側のOSを作り直すプログラム
そのものだった。
・自尊心の扱いと再構築
・心の空洞と向き合い満たす方法
・弱さを認め、受け入れる勇気
・ぶれない自分軸の育て方
・人に安心感を与える穏やかな在り方
・魅力が自然と滲み始める生活習慣
・思考が変わり、オーラが変わるプロセス
一つひとつの学びが、
今までの自分がいかに外側ばかりを追いかけ、
内側を置き去りにしてきたかを教えてくれた。
私はそこで初めて知った。
男としての魅力は、外側の装飾ではなく
内側の整いから立ち上がるのだということを。
この出会いが、
私の内面の再生を本格的に始める
最初の一歩となった。
●崩れた自分を一つずつ拾い集め、組み直した
私はまず、
自分の弱さを隠さないところから始めた。
強いふりをやめた。
平気なふりもやめた。
「大丈夫」という嘘もつかなくなった。
すると不思議なことが起きた。
今までのイキってたデュークより、
弱さを見せた素のデュークの方が、
周りから好かれ始めたのだ。
私は戸惑った。
弱さを見せれば嫌われる。
弱い男は価値がない。
ずっとそう信じてきたのに、
現実はまったく逆だった。
ここで気づく。
「あ、俺がモテなかったのは強さが足りなかったんじゃない。
弱さを認める強さがなかったからだ。」
今まで必死に隠してきた弱さは、
欠点ではなく、
むしろ人と心を通わせるための“入口”だった。
強さだけの男には、
人は寄ってこない。
弱さだけの男にも、
やはり人は寄ってこない。
強さと弱さが同じ場所にある男こそ、人に安心を与える。
崩れて散らばった自分の欠片を、
一つずつ拾い集めて、
ゆっくり組み直していく作業。
それこそが、
本当の再生の始まりだった。
この気づきが、
後に再生計画の基盤になっていく。
●そして、ついに完成した“理想人格モデル”
学びを深め、
崩れた自分を一つずつ拾い集め、
静かに組み直していく作業を続けるうちに、
私は少しずつ内側の変化を実感し始めた。
数ヶ月かけて、
感情・思考・行動・口癖・姿勢・価値観。
これらを一つひとつ丁寧に整えていった。
そんなある日、ふと鏡を見た瞬間だった。
「あれ? 俺……変わってる?」
気づけば、表情が柔らかくなっていた。
姿勢が整い、呼吸が深くなり、
どこか落ち着いた空気が漂っていた。
人との距離感が自然になり、
女性とのコミュニケーションも無理がなくなる。
その時、私は心の底で確信した。
モテるかどうかなんて、
顔でも収入でもファッションでもない。
モテとは、人格の設計図で決まる。
ここが崩れている限り、
どんなテクニックを使っても上手くいかない。
逆にここが整えば、
年齢も環境も関係なく、人生は立ち上がる。
私はその設計図を自分に適用し、
何度も書き換え、再構築していった。
やがて、自分の中に
揺るぎない軸のようなものが形になっていく。
・人に左右されない自尊心
・言い訳せず動ける思考
・相手に安心感を与える余裕
・自分の人生を楽しむための軸
・自然と滲み出る存在感
これらが、自分の当たり前になっていった。
運命の設計図を手に入れた日

そしてある瞬間、私は気づいた。
これが…理想人格モデルだ。
私はそこで悟った。
「俺が変われたのは奇跡じゃない。
変わる構造を理解し、再現したからだ。」
「ならば、この構造は
他のオジサンにも再現できるはずだ。」
「これ、俺だけの学びで終わらせていいのか?」
「同じように苦しむ男を救えるんじゃないか?」
そう思った時、
私の中でひとつの答えが生まれた。
プロセスがあるということは、
それは体系化できるということだ。
体系化できるということは、
誰かの人生を変えられるということだ。
私の失敗、崩壊、孤独、学び、再構築。
その全てが一本の線となり、
ひとつの設計図として形を成した。
私は確信した。
これさえあれば、人は何度でもやり直せる。
こうして誕生したのが、
モテオジ再生計画
だった。
今の私は54才。
「オジサンだから」という言い訳は、
とうに手放した。
20代のOL、30代の美容関係者、
40代のエステティシャン、
50代の小料理屋の女将。
幅広い女性たちと、
食事をし、芸術を楽しみ、自然に触れ、体に触れ(笑)
人生そのものを味わう時間を過ごしている。
もちろん、ここに辿り着くまでに
迷いも、遠回りもたくさんあった。
だが、その全てが
理想人格モデルを完成させるための道だった。
もしあなたが
「もうオジサンだから無理なんじゃ…」
「俺なんか相手にされない…」
「今さら恋愛なんて恥ずかしい…」
そう思っているのなら、
それは完全な誤解だ。
あなたの人生は、
ここからいくらでも立ち上がる。
もし本気で
「モテオジとして人生を楽しみたい」
そう願うなら、まずやるべきことは3つ。
1.理想人格モデルへ移行し、在り方を整える
2.外見を磨き、第一印象のインパクトを作る
3.人生の品格をワンランク上げる習慣を身につける
この3つが揃った瞬間、
人は必ず変わる。
そして、この3つを体系化し、
誰でも最短で変われるように設計したのが
モテオジ再生計画。
そして今──私はあなたに、たったひとつだけの道を用意しました。
あなたが
「本気で変わりたい」と少しでも思うなら、
ここからはあなた自身のペースで選んでほしい。
デュークによる無料個人面談
あなたの現状、悩み、過去の失敗、強み、生活習慣…
すべてを一緒に整理して、
あなた専用の再生ロードマップを作る時間です。
営業ではありません。
本音で話せる、完全プライベートな相談です。
・何から始めればいいか分からない
・自信が全然ない
・女性との会話が不安
・過去の恋愛で深く傷ついている
こうした想いを抱えているなら、
そのまま一人で抱え込む必要はありません。
どんな内容でも大丈夫です。
同じ痛みを通ってきた男として、
あなたの変わる一歩を、本気でサポートします。
【限定について】
・先着3名のみ受付
・48時間限定
面談の質を保つため、
これ以上はどうしても受けられません。
そのため、
ご希望の方は早めにお申し込みください。
下記ボタンより申し込みしてください。
申し込まれましたら、改めて私からご連絡します。
最後に、これだけ伝えたい。
人生は、
やり直しがきかないと思っている間は変わらない。
でも一歩踏み出した瞬間から、
景色がガラッと変わる。
その一歩が、
今回の個人面談でも、
他の方の面談でも、
何でも構わない。
大事なのは、
あなたが「変わりたい」と思った、その気持ちを無駄にしないこと。
あなたの人生の後半戦が、
今から最高のステージへ向かうことを願っています。
心から、あなたを応援しています。